[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
小3までに育てたい算数脳 高濱 正伸(著) 1575円

算数脳とは人生を切り拓いていく力
算数脳とは「人生を切り拓いていく力」という言葉に感銘を受けました。
大人になれば、ならっていないことばかりが待ち受けるのが人生です。
それを生き抜く力が算数脳ということでしょう。
大人にこそ読んで欲しい。
小学生を持つ親には目からうろこのことが多いです。
例えば、なぜ小学校入試で、「今日はどうやって来ましたか」と聞かれるのか。
また、音読と算数の関係など。
大人にも子供にも読んで欲しい本ですが、算数脳の決め手となる「外遊び」が
簡単に出来ない時代でもあり、今の子供たちがちょっとかわいそうになります。
誰に言ってるんですか?
この本は誰に向かって言ってるんでしょうか?
親が一流大学を出ていて、仕事は医者、弁護士、公認会計士、高級官僚、建築家、一流企業の社員・・・など、いわゆるエリート的な職の親だったら、子供に算数を教えられるかもしれないし、それ以前に、メンデルの法則により、親が優秀なら、子供の遺伝子が優秀である可能性が高いでしょう?親に学歴もなく、仕事も零細企業の肉体労働者とかだったら、算数脳だろうが、国語脳だろうが、理科脳だろうが、社会脳だろうが、体育脳だろうが、育てられる訳ないでしょ?そんなもん育てられるのは一部の親だけでしょ?教える方も優秀。教えられる方も持って生まれた素質があるのだから、育てたらそれだけ伸びるのが当然ではないか。
本自体が悪い内容ではないが、優秀なDNAを持った一握りのエリートにしか通用しない本だ。もしタイムマシンがあって、私が生まれる前に私の親に読ませたところで何の効果もないだろう。
均衡がとれてこそ美しく、安定します
算数は考える力、計算は単なる一部に過ぎない、外遊びや体験重視などの本書の主張に誰も恐らく反対しないでしょう。ただ、実際の子供に接しているとそう単純ではないのも事実です。子供によって、どうも出来不出来があるようだし、家庭の学歴も影響しているようだし、計算力もある程度ないとどうにもならないし・・さらに小3以降になると学習塾の存在も重みを増し、中学受験すべきかどうか、国公立か私立かどうかも段々視野に入り、親達の前には小学校教育について百家争鳴の光景が広がってしまいます。
著者の高濱氏は本書の至る所で思考力養成に重点を置いてあり、これは一定の知能以上を前提としており、むしろある水準以上の教養家庭向けとなっています。集団重視の学校が氏の方法を効率的にできるわけでなく、その意味ではむしろ、計算重視派の岸本氏が主張する《見えない学力》が育つ家庭でこそ高濱氏の主張が生きてきます。逆に、学校で無理に思考力中心にすると一定以上のゆとりが不可欠であり、同時に皮肉にもむしろ知能が高い?子供優先となり、授業では理解中心がモットーで同じことを繰り返しているに過ぎないと親が不満を持ち、計算力に向かってしまいます。その結果が現在であり、小学校は授業日数が増え、計算力も増やす方向にゆっくり向かっています。岸本氏が思考力を無視したわけではなく、多くが比較的貧しい家庭の子供達の中に計算力向上を通じて学力も向上させたという社会的功績があったということで、これに親が煽られて右往左往するくらいならば、むしろ先に本書を読んだ方が良いでしょう。とくに和差算や鶴亀算ができない、台形・円の面積の公式は知っていても、導き方を複数の方法で楽しく説明できない親の方は計算力偏重になりやすいようなので、均衡をとるために本書が必読となるかもしれません。
具体例がおもしろい
全体を通じて「外遊びの重要性」について説明されています。
例として、いわゆる「できる子供」たちが、外遊びを通じて培われる素質が充分でなかった為に伸び悩む様子が挙げられています。
小3までに外遊びをさせることが重要で、ドリルやペーパー漬けにする危険性が具体的にわかります。
なるほどと納得する記述がたくさんあり、おもしろかったです。
ただ「外遊び」さえ充分であれば勉強ができるとは限らないので、
「外遊びの後に勉強に引き込む工夫」が重要と思われますが、その点についてもっと記述にボリュームがあればなお良かったです。
それなりに参考になります
子育てに参考になることは色々書かれています。子供の姿を描いたエッセイも楽しい。
一方、「算数脳」を育てるのに外遊びが有効、ということにはそれほどの説得力はありません。純文系頭脳の自分も、幼少の頃は充分外遊びなりブロック遊びなり、やっていたはずですからね。日頃から空間把握のような能力は生まれつき個人差があるんじゃないかと感じていましたが、外遊びでその差が埋まるとはやはり思えません。ただ、少なくとも外遊びのメリットや、幼児期からドリルで詰め込み教育をやることの弊害は納得できました。
統計数字を疑う なぜ実感とズレるのか? 門倉 貴史(著) 777円

統計数字のマジックを解明
様々な、私たちが当然と思っている統計の不安定要因を解説している書である。
GDPから始まって、多くの統計資料が書き手の恣意によって偏向していく様を具体的に記述してくれているので、統計数字を鵜呑みにしないようにとの著者の意図が良く伝わった。
それにしても著者、門倉さんは著書出版のペースが速いですね!前著書「夜のオンナはいくら稼ぐか?」から3ヶ月しかたっていないのに、この書を出版するなんて、著者の将来性を楽しみにしている。感謝
この作者自体の統計の扱い方に疑問が?
まえがきにおいて、交通事故の死者数に関する統計の例を挙げて統計のウソの実例のように紹介していますが、この扱い自体に、作者による統計の恣意的な解釈の例がみられます。交通事故の死者数について、厚生労働省の数字と警察庁の数字はその定義が違うので、乖離があるのは事実です。しかしながら、厚生労働統計の交通事故死亡者数を調べてみると、警察庁の統計と同様に減少しています。数値が減少している統計に対して、同じ事象を扱っていながらも定義が異なっているために、常に多い数値を出す統計を取り上げて乖離があること(それは、定義が異なるので当然の乖離なのですが)をもって、「減少しているのは、統計のみせかけの現象だ」などと鬼の首をとったかのように述べていますが、この違いは少し調べれば分かるように統計の解釈の違いだけですので、作者が述べている「見せかけの現象」というのは、あきらかに間違いです。これだけでそれ以上の部分を読む気をなくします。まあ、「統計数字を疑う」というタイトル自体が、統計数字を疑うことがない人に対する警鐘だと思えば、その価値もあるのですかね。
著者の実体験に裏打ちされた経済統計解説
よくある「統計の常識を疑う」系の書籍だが、実際に経済予測等に携わった著者の経験が多分に反映されており、とりわけ第3章でのシンクタンクが試算する経済効果の胡散臭さや、第4章での統計の癖・バイアスに関する解説は白眉。一方で第2章の通説に関するコメントは(人によっては)首を傾げる箇所もあるが、こうした著者の主観が良くも悪くも本書の特徴となっている。仕事で経済統計を扱う向きならば、ほくそ笑みながら読み流せること請け合い。なお第5章は著者がライフワークにしている「地下経済」に関する話であり、若干蛇足な感はある。
ところで本書のレビューで「目が覚めました」「やはりGDPは信用できないんだ」といった類のコメントが散見されるが、こうした姿勢もまた所詮は"情報の鵜呑み"ではないか。本書の内容に対しても疑ってかかるくらいのリテラシーの高さが求められよう。
統計リテラシー向上にお薦め
平均寿命、経済効果、景気動向等、普段は算出結果のみを意識しがちな身近なデータについて、導出過程から考える事により理解が深まります。
実際に統計数字を駆使するエコノミストだけあって記述が具体的で分かり易いです。
景気動向の指標には実感しづらい部分がありましたが地下経済活動にも触れており最後まで一気に読めました。
数字をとらえるセンスが身に付く!
著者のこれまでの経験をもとに、統計数字をどのように解釈すればいいかを指南してくれる。
難しいところを読み飛ばして、わかるところだけを読んだが、結構面白かった。
「なるほど」と思うようなところがたくさんあったよ。
不完全性定理―数学的体系のあゆみ (ちくま学芸文庫) 野崎 昭弘(著) 1155円

カントール対角線論法との関係性
不完全性定理の肝であるゲーデル数が、カントール対角線論法の応用であるということが明示されているという一点において、近年最良のゲーデル入門書だ。
ヴィトゲンシュタインのいう「見渡す」効果を最大限利用したということができる。
ゲーデル入門にはまず本書のカントール関連の記述から、と推薦しておきたい。
手軽に読める本
古代史の中で数学がはじまってから、不完全性定理が見出だされる、現代までの数学の流れがわかりやすく書かれています。
数学の込み入った予備知識がなくとも、数学自体を議論するために超数学が生まれ、その中で不完全性定理が現れた雰囲気はよく伝わってきました。証明に関しては、ある程度簡略化されてありますが、なんとなく納得できる論理の展開がなされています。
肝心の不完全性定理は最終章のみで扱われているので、不完全性定理だけを特に知りたいという方には物足りないかもしれません。
数学の意外なおもしろさ満載
まず、ゲーデルの不完全性定理の入門書として、質、コストパフォーマンス(安い!)ともにベストだと思います。わかりやすい上に、概念だけでなく、自分でも証明を追えるようになっています。
ゲーデルに限らず、集合論の大切さなど、数学の概念的な面白さや、数学者の意外な生涯(カントルの悲劇というか)などについての記述も充実していて、数学のおはなしとしても楽しめます。
ゲーデルの不完全性定理、チューリングマシーンをめぐるさまざまな
解釈についても触れてあり、自分で考えるきっかけにもなります。
難しいところは読み飛ばしました。
「ゲーデル、エッシャー、バッハ」の訳者の方がゲーデルの超入門書を書いた、と裏表紙にあったので、今度こそと思って読んでみた。
「はじめに」にあるように1から3章は数学の歴史である。ユークリッドについて本当に平易に書いてあり飛ばして読める。超数学入門の後半の3章は著者のお勧めに従いかなり読み飛ばした。「6章 ゲーデル登場」で、よし真面目に読むぞと思った。
かなり平易に書いてあると思うが、とにかく証明部分が難しかった。わかったような気にはなる。が、よくよく考えると著者の噛み砕いた日本語の説明部分にうなずいている。数学を日常にしている人にはもっと判りやすいのかもしれない。
ゲーデルの不完全性定理は、普通の言葉に訳してよく引用される。「人間の知性の限界が示された」とか「完全ではない」とか文章では簡単に書かれるが、やはり数学的に数式とか論理式で証明を導けないと判ったとはいえないのではと思っていた。その意味で読んだ後も読む前と変わらず解っていないが、途中色々数学の興味深い話があり全体として面白かった。(眠いところも多かった。)ゲーデルの不完全性定理は、「新しい理論の始まり」になったという。漠然と、数学って破綻しているんじゃとずっと心配していたので、ここを読んだだけでも良かった。
初心者向きではない
肝心の不完全性定理について、ページ数が少なく、説明もあまりていねいとはいえず、なぜか、ものすごく細かい字で対角線論法の説明がされている。初心者というより、一般向けとしても、不親切な感じを受けた。
忘れてしまった高校の数学を復習する本―高校数学ってこんなにやさしかった!? 柳谷 晃(著) 1470円
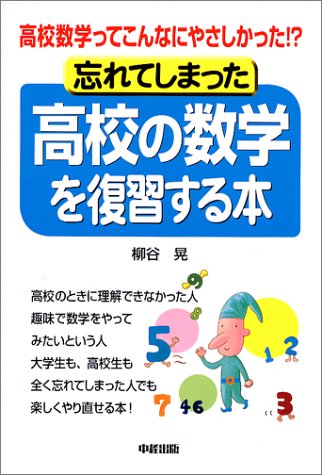
考え方が分かります。
現在理系の大学に通っていますが、
高校時代数学は得意でした。
それが大学に入って数学を使わなくなり、
だんだんと忘れていってるのを実感して
やばい!と思い短期間で復習する為に購入しました。
受験生の時は量をこなしていれば
問題の型が見えてくるのでテストで点は取れますが、
原理についてはなかなか知る機会がないのではないでしょうか。
塾で高校生に数学を教えているのですが、
教える立場になって初めて原理の理解の必要性を感じました。
この本は「何故そうなるのか」というところを
きちんと説明してくれているので大変助かっています。
特に指数・対数関数のところは参考になりました。
文系・理系どちらでも数学でちょっとつまずいているという
学生さんにはよろしいかと思います。
なかなか
忘れていた公式とか解法を思い出させてくれるだけでなく、「そうだったのか」と
改めて理解させてくれる良書です。
単純な計算を大量に解く、いわゆる「脳トレ」もいいですが、高校数学くらいの方が
やってて面白いですね。
本当にざっと流す程度なので、一日で読み終えちゃいます。
「最近脳をあまり使ってないなぁ」という人向けかも。
高校数学が簡単に分かりやすく書かれてある良書。
正直、内容をあてにはしていませんでしたが、購入して問題を解いてみると
以外にも簡単で分かりやすいので驚いています。買ってよかった本です。
但し、ベクトル等は載っていません。
主要部分を網羅しただと思います。高校数学の全過程は載ってはいません。
そして、とっつきにくいであろう「三角関数」「微分積分」と「新しい幾何」が平易に記載されていて、
それが案外分かりやすかったのは良かったです。
微分積分って文系の人間には一生縁が無かったりするので、この機会に基礎の基礎を触れただけでもいいことだと思う。
学校で配られる教科書よりも分かりやすいかもしれません。
問題も解説も無駄が無くシンプルですので、混乱することなく問題が解ける。
そこが良いと思います。
高校数学のポイントを速習したい方やこれから始める方が概観するのには最適!!
文系学部出身で高校数学を再学習している社会人です。
第1章「式の計算」から第13章「新しい幾何」(ガウス平面)まで、
若干旧課程の分野も含まれていますが、ほぼ新課程数2Bまでの内容の基礎を
平易に解説しています。
数学好きの中学生から社会人まで基礎の基礎を肩肘を張らずに学びたい方の
良ききっかけになる数少ない本だと思います。
因みに、評者は時には鉛筆で書きながら読みました。
蛇足ですが、本書の読後、数3の分野は『高校の微分積分を復習する本』に進みました。
数学嫌いの人でも微分積分できるようになる本。
すごいわかり易い、高校の時数Tしかとってなかったのにもかかわらず、最後まですんなり進めることができました。簡単な問題ばかりで苦になりませんでした、高校のときあんなに数学が嫌いだったのに、すこし数学が好きになりました。
遥かなるケンブリッジ―一数学者のイギリス (新潮文庫) 藤原 正彦(著) 460円

イギリスから学ぶこと。
相変わらず面白い文章を書くので敬服しますね。「若き数学者のアメリカ」のとおり20代後半からアメリカ被れになった著者が、40歳を越えてからイギリスで1年間暮らして判った両国の違い。宗教、マナー、騎士道、人種差別、男女関係など等色々な観点から違いを感じていく。読んでいると結構イギリスに行って見たいような気がしてくるものである。食事の拙さが判っていてもね。経済の話題はアメリカだし、食物はフランスだし・・・。今までのアメリカ万歳からイギリスを通して日本の良さを再認識していったという流れは興味深いですね。ホントに日本は単純なアメリカ指向が是正されない国なのかもしれません。むしろアメリカよりも伝統を壊していくのが平気なのでは?と感じる昨今ですが・・・・。「国家の品格」にあるように武士道や日本語教育は大事ですね。
才能があったり,コネがあったりすると,いいなぁ
数学者としては文章は読ませる。文章は,種類こそ違え,森毅と同じくらい面白い。「遥かなるケンブリッジ」という題名も素人にはイメージ喚起的だ。最初の2章はイギリスの門前で,第三章から第九章まででイギリスに入場しており,最終3章で,溶け込んだイギリスの感想を述べるという構成。
イギリスの大学の様子や数学者たちの人間的な側面などがよくわかるが,私などは業界の人間ではないので,世界規模で有名な人物の人となりもただの登場人物に過ぎない。藤原のイギリス(人)評価は,イギリス人数学者には当てはまるかもしれないが,下層のイギリス人にはまずは当てはまらないだろう。国民性評価なんていい加減なもんだ。言いたい奴らが言いたいように言って,納得したがってる奴が納得しているという構図で,これといって根拠がない。統計的なウラなんかまずはない。そもそも,たとえば“国を理解する”という状態を成り立たせる条件はいったいなんだろうか? もしその国に住むことが条件であったりすれば,殆どの人に国は理解できない。とすれば,評価はまず不能だ。頭が悪くとも,こっちは向こうに住んできたんだ,だから僕のほうが正しい,なんて凄まれれば,周囲がアホなら勝てる見込みはまずない。もっとも,勝つことには意味はないのだが。
本書は1988年7月刊行の(ってことは帰国と殆ど同時)文庫本化。解説は南木圭士(作家・内科医)(1057字)
秀逸なエッセイ
藤原氏のエッセイは「若き数学者のアメリカ」に続いて2作目です。
アメリカ留学時は独身だった著者も、妻を迎え、3人の子供の父親となっており、その分視野がぐんと広がっています。誰が読んでも価値あるエッセイだと思います。
自分の大学の同僚、隣人、家族を通しての友人のイギリス人たちとのユーモアあふれる会話。
天才的数学者リチャードの「イギリスで最も大切なのはユーモアだ」という言葉通り、彼らが藤原氏とのユーモアあふれる会話を楽しんでいた様子が目に浮かぶようです。
その会話から読み取れるイギリスとイギリス人の様子。著者の押し付けがましいイギリス観などはありませんが、数々の会話から、イギリスというものを、読み手が自然と考えさせられるような、すばらしいエッセイです。
特に大学の授業、教授達、学生については詳しく書かれており、留学される方には参考になるのではないでしょうか。
文章もいきいきとしていて、とても読みやすいです。
英国の大学内情
英国での1年間の研究留学する機会を得た日本人研究者の滞在記。日本の大学では雑務が多いため、集中して研究できると意気揚々としてやってきて、ケンブリッジやオックスフォードでの講演でのその分野の権威の前で恐れつつも立ち向かう様子、そして、英国の研究者との交流。
アメリカの大学滞在記"若き数学者のアメリカ"と読み比べるとなお興味深いです。イギリスとアメリカの違い、数学者として家長としてそれなりの自信を持った著者の行動。また、国家の品格につながる愛国心がところどころに書かれています。
なかなかイギリスの大学について書かれている著書はないので英国留学を考えている人、英国か米国か留学先を迷っている人は読んでみると良いかもしれません。
イギリスとイギリス人を知ることで日本と日本人を知る。
私も他のレビュアーの方と同じく、「若き数学者のアメリカ」
が面白かったので、こちらも読み始めた口です。
ケンブリッジでの生活、キャンパスでの教授の人間描写、次男
のいじめから人種差別を考え、その対応etc.全編がエッセイなの
でさくっと読めます。
第七章のレイシズムからが特に面白かったです。イギリスの階
級社会の問題点を読む新聞から考察しているところなどは、なる
ほどと思いました。
第12章のイギリスとイギリス人も興味深いです。ユーモアを
大切にし努力をひけらかすことを嫌う国民性。私はイギリス人の
友人はいませんが、なんとなく頭の中にイメージがわきあがりま
した。
こんなジョークが書いてありました。
無人島に男2人と女1人がたどり着いた。
もし男がイタリア人だった場合、殺し合いが始まる。
フランス人だった場合、一人は夫婦、一人は愛人として話がま
とまる。
イギリス人だった場合、口をきかないので何もおこらない。
日本人だった場合、東京本社にFAXで指示を仰ぐ。
世界各国で文化や国民性が違いますが、だからこそ面白いとも
思います。旅行に行くのも新しい友人との出会いも、そのような
「違い」を認めるところにあると思います。自分との異質性を認
め、自己の見識を広める。読後にこんなことを感じました。
